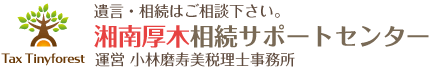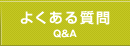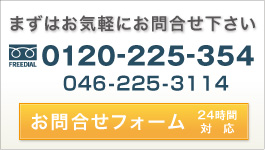Author Archive
遺産分割未了のまま第二次相続が発生した場合
相続税の相談を受けておりますと、いろいろなケースに当たることとなります。
先日は、父が亡くなったあと、相続手続きを終えないうちに、母が亡くなってしまったという事案でした。
もし、母の死亡に係る相続税の申告期限までに、父の遺産について母の取得分を零とする遺産の分割が行われているときは、相続人である子たちは、母の死亡に係る相続税の申告をする必要はありません。しかし、母の死亡に係る相続税の申告期限までに父の遺産が未分割である場合には、父の遺産のうち、母の法定相続分2分の1に相当する部分について、母の遺産として相続税の申告をする必要があります。
ところで、相続税額の計算では、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6千万円のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという特例があります。
これが、配偶者の税額軽減特例というものですが、被相続人の遺産が未分割ならば、この特例の適用は受けることはできません。
ご相談の事案のように、父の亡くなったあと母がすぐに亡くなった場合、母は父の死亡に係る相続税の申告について、配偶者の税額軽減特例を受けることはできないのではないかという疑問が生じます。
このような事態に対応して、相続税法基本通達19の2-5では、相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割される前に、その相続(第1次相続)に係る被相続人の配偶者が死亡した場合において、第1次相続により取得した財産の全部又は一部が、第1次相続に係る配偶者以外の相続人等及びその配偶者の死亡に基づく相続に係る相続人等によって分割され、その分割により配偶者の取得した財産として確定させたものがあるときは、配偶者の税額軽減特例の規定の適用に当たっては、その財産は分割により亡くなられた配偶者が取得したものとして取り扱うことができるとしています。
つまり、子ども達が、父の遺産の一部を母が取得したものとして確定させれば、それについては配偶者の税額軽減の特例が使えることとなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
債務控除と医療費控除
国税庁ホームページに、質疑応答事例の新着情報が掲載されています(平27.11.25)。
今回は、所得税関係が中心で、医療費控除に関するものもあります。借入金で支払った医療費、共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合、父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合の3問です。
ところで、医療費については、相続税の申告でもでてきます。被相続人の死亡の際に、相続人が支払った医療費は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものですので、相続税額の計算上、債務控除の対象とされます。
ここで、被相続人の最後の所得税の申告、準確定申告について考えてみます。被相続人が死亡後に、被相続人の財産から被相続人の医療費を支払った場合、これは、被相続人の所得税の準確定申告で医療費控除の対象となるのでしょうか?
答えは否です。
その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。
ですので、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないということになり、被相続人の医療費控除の対象にすることはできないのです。
では、相続人が支払い、相続税の申告で債務控除の対象とした医療費を、重ねてその相続人の所得税の確定申告で、医療費控除の対象とすることはできるのでしょうか?
所得税の医療費控除の要件は、医療費を支出すべき事由が生じた時、つまり治療を受けたとき、又は、現実に医療費を支払った時の現況において、その対象とある親族(ここでは、被相続人)が、支払った人と生計を一にしていること、となります。
したがって、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人が受けた時に、その支払った親族が被相続人と生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人であるその親族の医療費控除の対象にもなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
前受家賃と債務控除
不動産の賃貸契約では、翌月分の家賃を当月末日までに支払う契約になっていることが多いようです。
で、地主さんの相続では、この前受家賃が、相続税の申告上、債務控除の対象となるか疑問となります。この家賃については、まだ役務の提供、すなわち、賃貸物件の提供前に支払を受けたものですから、少なくとも、賃貸人は賃借人に債務を負っているということになりますよね。
では、この1か月分の家賃は、賃貸人である被相続人の債務として、債務控除の対象となるのでしょうか?
答えは否です。なぜならば、家賃の前払いを受けた賃貸人は、賃貸借契約に従ってその不動産を使用させるという債務(義務)があるのみで、賃貸人側が一方的にその賃貸借契約を解除するなどの場合を除き、その前払家賃の返還義務を負っていないとされているからです。
すなわち、前受家賃自体には債務性はあるが、それは、対応する期間について、家屋を使用させるという義務だけなので、一般に債務控除の対象とはならないということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
土地建物の交換をしたとき
土地や建物について、使い勝手などの理由から、他の方が所有する同じような土地や建物に交換することもよく行われています。よく行われるのが近接地の交換で、話し合いで行われることが多いようです。
その際に、気になるのが課税関係で、当事務所でも事前に相談を受けることがあります。
個人が、土地や建物などの固定資産を同じ種類の固定資産と交換したときは、譲渡がなかったものとする特例があり、これを固定資産の交換の特例といいます。
この特例を受けるためには、次の6つの要件を満たす必要があります。
(1) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
(2) 交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
(3) 交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4) 交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5) 交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
(6) 交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。
この特例の適用にあたって、不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産は、棚卸資産となるため、対象になりません。
で、このうちの(6)の要件について。交換譲渡しようとする土地の価額が500万円で交換取得しようとする土地の価額が400万円の場合、普通は取得しようとする土地の他に100万円をもらい、交換契約を成立させます。
この実際にやりとりする100万円を交換差金といいます。これは、高いほうの土地の価額500万円の20%以内ですから、この(6)の要件を満たします。
でも、交換譲渡しようとする土地の価額が500万円で、交換取得しようとする土地の価額が300万円ならば、時価の差額は200万円となって、500万円×20%=100万円より大きいので、(6)の要件を満たしません。
それならば、500万円の土地のうち、持分5分の3を交換とし、5分の2を売買とすることができるならば、少なくとも5分の3部分は、譲渡所得税は課税されないのではないかと思う方がいます。このスキームはOKでしょうか?
これについては所得税基本通達58-9に次の規定があります。
「一の資産につき、その一部分については交換とし、他の部分については売買としているときは、法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) の規定の適用については、当該他の部分を含めて交換があつたものとし、売買代金は交換差金等とする。」
この規定のポイントは「一の資産」にあります。上記の例では、「500万円の土地」が「一の資産」に該当します。ですので、上記の例では、全体として、交換特例の適用はありません。
では、建物とその付属設備を一体として交換した場合、付属設備の部分だけを売買とすればどうなのかという疑問が生じます。
この場合の結論もNO!です。交換特例の適用にあたっては、建物に附属する設備及び構築物は建物の種類に含まれることになるため、建物とその附属設備を一体として交換した場合は、建物とその附属設備で「一の資産」となるからです(所得税法58条1項2号)。
それならば、土地については交換契約を締結し建物については売買契約を締結した場合はどのようになるのでしょう。それが、国税庁のHPに照会事例として掲載されています。
「甲は乙との間で、甲所有のA土地と、乙所有のB土地との交換契約を締結するとともに、A土地の上に存する甲所有のC建物については、乙に売買する旨の売買契約を締結することを予定しています」というものです。この場合も売買代金が交換差金として取り扱われるのでしょうか?
結論から申しまして、その場合はこの売買代金が交換差金として取り扱われることはありません。
というのは、さきほどの「一の資産」とは、所得税法58条1項各号に掲げる資産の種類の区分ごと(すなわち同一資産の種類ごと)の資産をいいます。
それぞれの資産の種類は次のようになります。
一 土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
二 建物(これに附属する設備及び構築物を含む。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)
つまり、土地と建物は別の種類の資産となりますので、土地については交換特例を適用し、建物については売買契約により譲渡しても、全体で交換を行ったとして、課税されることはないということとなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
未支給年金
相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集では、興味深い事例が掲載されています。
事例7は「所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合」です。この回答は、「所得税の準確定申告に係る還付金は、被相続人(父)に帰属する財産であり、相続財産に該当するため、第11表に記入します。」で、理屈を考えて納得される方も多いことかと思います。
ところが、事例8は「支給されていなかった年金を受け取った場合」で、回答は「未支給年金については、被相続人の遺族が、未支給年金を自己の固有の権利(その者の権利)として請求するものであり、被相続人の死亡に係る相続税の課税対象にはなりませんので、第11表には記入しません。」。これって、えっ、と思われませんか?
なぜ、遺族の固有の権利となるのでしょう。
その根拠は厚生年金法37条にあります。それには、「保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。」とあります。つまり、
(1) 未支給年金は、受給権者の死亡後に、遺族の請求に基づく裁定があって初めて社会保険庁の年金支払義務及び支給金額等が具体的に確定すること。
(2) 裁定の請求を行う者は遺族であり、年金を支給する旨の通知(裁定があったこ との通知)は、遺族に対して遺族名義で行われること。
(3) 仮に死亡した受給権者に未支給年金に係る債権が帰属すると考えた場合、遺族の法律行為(請求)に基づいて既に死亡している受給権者に法律効果が帰属することになり相当でないこと。
これらの理由により、相続財産ではなく、遺族の固有の権利とされているのです。
また、平成7年11月7日の最高裁判決でも、「国民年金法19条1項は、『年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。』と定め、同条5項は、『未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。』と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである。」としています。
では、税法の規定はどのようになっているのでしょうか?
それは、相続税法でなく所得税法についての基本通達にあります。
所得税基本通達34-2(遺族が受ける給与等、公的年金等及び退職手当等)
死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等で、その死亡後に支給期の到来するもののうち9-17により課税しないものとされるもの以外のものに係る所得は、その支払を受ける遺族の一時所得に該当するものとする。
そう、遺族の所得税の対象となるのです。もっとも、一時所得の金額は、「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」で求められますので、他の一時所得、例えば、生命保険の一時金などがない場合、実際に課税価額に算入されることはないのではないかと思います。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
未納固定資産税
国税庁のHPの「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(平27.11.9)についてです。
事例14「未納の固定資産税・住民税」は、被相続人の未納の税金が債務控除の対象となるというものです。
解説がありました。「固定資産税と住民税の納税義務は既に成立しているため、相続開始日に納税通知書が送付されていない場合であっても、被相続人(夫)が亡くなられた年分の未納となっている固定資産税や住民税(注)は債務控除の対象となる債務に該当しますので、第13表に記入します。」
これらの税金は、1月1日の所有者や居住者について課されるものですので、このような結論となるのです。
で、間違いやすいのは、地主さんの相続案件です。
地主さんの相続案件の場合は、相続税の問題もさることながら、亡くなられた方が営んでいた不動産賃貸事業の経費の問題が出てきます。この事業は、相続人に承継されることとなりますので、未納の固定資産税について、亡くなられた方の、亡くなられた年の所得の計算上、必要経費となるか、事業を承継された相続人の不動産所得の必要経費となるか、迷うところです。
所得税の必要経費においては、その年の12月31日までに申告等により納付すべきことが確定した公租公課が対象となります。そして、年の中途において死亡又は出国した場合には、その死亡又は出国の時までに確定したものとなります。したがって、固定資産税や不動産取得税については、納税通知書が被相続人の生前に届いた場合だけ、被相続人の準確定申告における不動産所得の必要経費となります。
ここが、相続税と所得税の違いとなりますので、混同しないようにしなければいけません。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
夫婦連帯住宅ローン
国税庁のHPに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(平27.11.9)が公表されています。
おそらく、一般の方がご自分で申告されることを想定したものだと思いますが、次のような項目があります。
被相続人の兄弟姉妹が相続した場合(2割加算1)、被相続人の孫が相続した場合(2割加算2)、被相続人と養子縁組を行った孫がいる場合(基礎控除)、生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)、被相続人以外の名義の財産(預貯金)…等々。
これらについて、解説や根拠無しで結論だけ端的に示しており、それなりに有用な情報となっています。
この中で、今回は、「団体信用生命保険契約により返済が免除される住宅ローン」をとりあげましょう。
結論として、この住宅ローンは相続税額の計算において、被相続人の財産から控除できる債務、つまり、債務控除の対象とはなりません。債務控除の趣旨が、納税者の担税力を慮ったものということにあるところからも、それは当然のことですが、根拠としては、昭和44年5月26日付国税庁長官通達「団体信用生命保険にかかる課税上の取扱いについて」があります。
したがって、一般的な住宅ローンについては、相続税の申告において何も考慮する必要はありません。
では、ここからが応用問題です。
ご夫婦で住宅を購入された場合に、夫婦連帯住宅ローンを組むことがあります。このローンは、保険契約者及び保険金受取人を金融機関、被保険者を連帯債務者である夫婦とする団体信用生命保険契約を、一般的な住宅ローンに付けたものです。この保険契約により、ご夫婦のいずれか一方の方が死亡又は高度障害となったとき、住宅ローンの全額が免除されることとなります。
この場合も、一般の住宅ローンと同様に、どちらか一方に相続が発生した場合の相続税の申告で、何も考慮しなくていいのでしょうか?
生存されている住宅ローンの連帯債務者は、亡くなられた連帯債務者の死亡により、自身の債務の免除を受けることとなります。
そして、住宅ローンの生存配偶者負担分について、支払義務が消滅したことについては、相続税法8条のみなし贈与の規定「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除等を受けた場合」に該当します。つまり、その部分は死因贈与を受けたとして、相続税の課税価格に加算されると考えるのが適当となります。
結論として、夫婦連帯債務の住宅ローンがある場合は、生存配偶者については、自身が負担すべき住宅ローンの残債分の利益を被相続人から受けたとして、相続税の申告をすべきということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
被相続人に係る債務・債務控除の留意点
どのような相続であっても、債務の引継ぎのない相続というものはありません。とはいえ、相続税の申告においては、まずは資産の評価について心が奪われ、債務の取扱いについては、おざなりとなることも、ありがちなことのようです。
というわけで、本日、「被相続人に係る債務・債務控除の留意点」について、研修会の講師を務めさせて頂きました。
中野サンプラザという大きな会場での研修で、たくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございました。
研修では、実際に債務控除が争点となった裁決例、裁判例を多く取り入れ、実務での留意点を中心にお話させて頂きました。やはり、プロの方対象の研修会でしたので、地主の方の相続事案で、不動産所得との絡みがある部分などにご興味を持たれた方が多くいらっしゃったようです。
具体例につきましては、ここでも、順次、公開したいと思います。
また、「相続税申告で迷いがちな債権・債務」という本も、今年1月に清文社にて出させて頂いておりますので、あわせてご参考にしていただければ、と思っております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺留分減殺請求と生命保険金
遺言で財産を遺す方を決めても、気にかかるのは、相続人に保証されている遺留分です。
ところで、相続税の申告では、死亡保険金も相続財産に含めます。これは、被相続人の死亡により取得するものですので、税法では、その性質に着目して、相続財産とみなして、相続税の対象とするものです。
つまり、死亡保険金が相続財産と同様に取り扱われるのは、あくまでも税金計算上のことで、もともと相続財産ではありません。
したがって、遺留分減殺請求の対象とはなりません。
このことを利用して、生命保険契約をし、財産を遺したい方を死亡保険金の受取人とする場合があります。
ところが、被相続人の死亡により、保険会社から受け取った金銭が、死亡保険金とは限らないことにも注意する必要があります。
医療保険のなかには、保険金が給付される事由には、被保険者の死亡が含まれていない場合があります。このような保険では、被保険者の死亡で、保険契約自体が解約となり、保険会社からは、死亡保険金でなく、解約返戻金が支払われることとなります。
つまり、保険契約者と被保険者が同一人の場合において、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の返戻金は、みなし相続財産でなく、被相続人の本来の相続財産ということとなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
死亡保険金と代償分割
被相続人が結婚前に加入した生命保険の死亡保険金の受取人が、実家の親名義となっていることがあります。でも、被相続人に子がいる場合など、受取人となった方も、孫を差し置いて保険金を受け取りたくないとお考えになることが多いようです。
「保険金受取人の変更は、保険契約者の一方的意思表示によって効力が生じ、その意思表示は必ずしも保険者に対してであることを要せず、新旧受取人のいずれに対してもよく、これによって直ちに効力を生じ、保険者への通知は保険者に対する対抗要件にすぎない」とした最高裁判決があります(昭62.10.29最高裁判決)。
つまり、保険契約者が生前ならば、一方的意思表示で、死亡保険金の受取人を変更することができるということです。
では、遺言により生命保険金の受取人を相続発生後に変更することができるのでしょうか。
最高裁判決から、被相続人の意思表示が証明できる場合は、受取人を遺言により変更することができると考えられています。実務においても、生命保険会社の事務手続きで、遺言による変更を認めている保険会社が増えてきているようです。
一方、被相続人の意思表示が証明できない場合は、生命保険金の受取人の変更はできないのでしょうか。例えば、生命保険金の受取人となっていた被相続人の母が、その保険金を孫に渡したならば、贈与とされることとなるのでしょうか。
実はこれ、まだ、駆け出しの資産税担当者であった私が、かつて遭遇したものです。幼い子供を残し、被相続人が早世した事案でした。税務署をはじめ、いろいろなところで相談し、また、いろいろな本を調べました。
結論として、この事案では贈与税は課税されないということとなります。その理由として、このような場合、被相続人の意思として、やはり自分の子供に保険金を受け取ってもらいたかったであろうこと、そして、相続人の皆の意思として、生命保険金を孫に渡したとしたら、それは、代償分割として整理することが可能であることをあげることができます。つまり、共同相続人の全員で、生命保険金に相当する金銭を代償財産とする代償分割による遺産の分割方法を選択したとすることができるのです。
この場合の相続税の申告は次のようになります。
○ 契約上の受取人
生命保険金全額をみなし相続財産として相続財産に加算し、受取保険金を代償財産として相続財産から減算
○ 受取人としたい相続人
代償債務として取得した生命保険金相当額を、本来の相続財産とする。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。