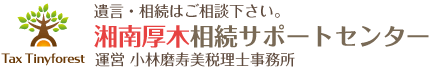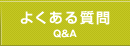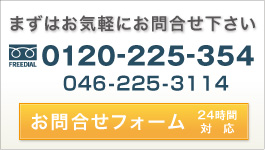Author Archive
明日(2/14)バレンタインデーは相続カフェの日です
明日(2/14)は相続カフェの日です。
確定申告のシーズンで税金についての関心も高まっているところ、お出かけがてら、当事務所にもおいでになりませんか?
生前贈与について、土地や建物の譲渡について、共有不動産の分割について、相続や不動産の評価について、そして、生命保険契約の取扱いについて…。
本当に、この際ちょっと聞いてみようといったことでも結構です。
美味しいお茶とお菓子をご用意しています。どうぞお気軽においでください。
※時節柄若干予約が入っております。お昼過ぎですと、14:30~においでください。また、予約不要の相続カフェの日ですが、046-225-3114宛お電話頂けましたら、状況をお話しできます。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続人の中に障害者がいる場合の相続税額の計算
相続税額の計算では、算出相続税額から、税額控除できる次の6つの特例があります。
(1) 贈与税額控除、(2) 配偶者控除、(3) 未成年者控除、(4) 障害者控除、(5) 相次相続控除、(6) 外国税額控除
相続をした人の事情により、相続税額からこれらの6つの税額控除をマイナスして納付税額を抑えることができます。
一般的によく使われるのは、配偶者控除(配偶者の税額軽減)です。
配偶者控除とは、配偶者の取得財産の価額が、1億6000万円と配偶者の法定相続分のどちらか高い金額まで非課税となる制度です。
そして、よくいわれることが、とはいえ次の相続を考えた場合に、配偶者控除の上限まで配偶者の取得財産を持っていくことは、お勧めできないということです。
つまり、配偶者は被相続人と同世代のため、取得した財産が次の相続の相続財産に含まれることとなる可能性が高く、第1次相続と第2次相続をトータルに考えた場合、却って税額が多くなってしまうというのがその趣旨となります。
ところで、ここでは、配偶者が障害者の場合の、税額控除の利用について考えてみます。
障害者控除とは、財産を取得した相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができる特例です。
この特例を受けることができる人は次のすべての要件を満たす人です。
(1) 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(2) 相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
これらを満たす人は、満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円(特別障害者の場合は1年につき20万円)で計算した額を算出相続税額から控除できます。
そして、この障害者控除については、面白い特例が付されています。上記のようにして計算した障害者控除額が、その障害者本人の「算出相続税額」より大きいため控除額の全額が引き切れないときは、その引き切れない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くというものです。(同様な特例が、未成年者控除にもありますが、ここでは触れません。)
つまりは、何らかの財産を取得した相続人の中に、日本国内に住所がある法定相続人である障害者がいるならば、その者の障害者控除の金額を、障害者本人だけでなく、扶養義務者である他の相続人の相続税額から控除できるのです。
この場合の扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
相続税額の計算は、最初にご紹介した(1)~(6)の順番で行います。しかし、障害者控除を活用しようと思う場合は、配偶者控除の利用の前に障害者控除の全額利用を考えます。
そのうえで、配偶者控除の利用額を考えることとなります。それは、配偶者が障害者である場合も同じで、配偶者控除と障害者控除はダブル適用ができるのです。
極端な例として、相続財産が1億6000万円以下の場合に、すべての財産を配偶者が相続するとします。その場合は、障害者控除を利用する余地はありません。そして、第二次相続がおこった場合は、配偶者が取得した財産が相続財産に含まれることになります。
しかし、第一次相続で、障害者控除額に対応する財産を子が取得することとし、残りを配偶者が取得することとした場合は、第二次相続に含まれることとなる配偶者の取得財産を少なくすることができます。
子が、被相続人の配偶者、つまり親を扶養する義務があること(扶養義務者であること)は、言うまでもありません。
また、子にとっても、残された親の扶養義務を果たす上でも、ある程度の財産を取得した方が、安心ということになります。
上記は単純化した例ですが、このように遺産分割においては、それぞれの相続の事情を踏まえて、何通りかのシミュレーションをして、考えてみることが大切となります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続により取得した上場株式等を譲渡する場合
被相続人が所有していた上場株式等を譲渡したときにも、所得税の申告が必要となります。この場合の取得価額は、被相続人の取得価額を引き継ぐこととなります。とはいえ、被相続人の取得価額が分からないことは珍しくありません。株式の譲渡所得の金額は、売却金額から取得価額と売却手数料を差し引いて計算するため、取得価額が分からないと困ったことになります。
取得価額が分からないものを譲渡した場合に、取得価額の額を売った金額の5%相当額とすることができるという特例がありますが、それだと売買金額のほぼ95%に対して税金がかかってきます。なんとか実際の取得価額を知りたいところです。
国税庁のホームページでは、取得価額は次のようにして確認できるとあります。
1.証券会社などの金融商品取引業者等から取引報告書が送られてくる場合
この取引報告書で確認できます、その他には、取引残高報告書、月次報告書、受渡計算書などの書類で確認できる場合もあります。
2.取引した証券会社が分かる場合
証券会社の「顧客勘定元帳」で確認できます。過去10年以内に購入されたものならば、取引した証券会社に問い合わせます。会社によっては、10年より前の取引情報が保存されている場合もあります。
3.日記帳、手帳、メモなどがある場合
これらがあれば、その金額で計算して構いません。また、取得時期のみが確認できる場合には、その取得時期を基に取得価額を算定しても差し支えないとしています。
4.1~3のどれによっても確認できない場合
名義書換日を調べて取得時期を把握し、その時期の相場を基に取得価額を算定します。
例えば、発行会社(株式の発行会社が証券代行会社に名義書換業務を委託している場合にはその証券代行会社)の株主名簿・複本・株式異動証明書などの資料を手がかりに株式等の取得時期(名義書換時期)を把握し、その時期の相場を基にして取得費(取得価額)を計算することができます。
これは、株券電子化後手元に残った株券の裏面で確認しても差し支えないとしています。
相続により取得した株式を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、課税された相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
この特例を受けるためには確定申告をすることが必要です。
確定申告書には、相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)、相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】)や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書などの添付が必要です。
取得費加算額はこの計算明細書で計算できますので、トライしてみて下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
リフォームはいつやるか~空き家控除その2
平成28年度税制改正により、空き家控除という譲渡所得の特例の導入が見込まれています。
この特例適用のためには、相続財産である家屋が現行の耐震基準を満たしていない場合、基準を満たすようリフォームをすることが必要でした。
しかし、当然のことながら、リフォームのためには資金も要することから、相続税が課税される事案では、相続開始前にリフォームをしておくのはどうだろうかという疑問がでてきます。
被相続人となる方の財産として、自宅と預貯金があるとします。リフォームにより預貯金が工事費用分減少しますが、それがそのまま建物の評価額にオンされるかというと、相続税の計算上はそうはなりません。
建物の相続税評価額は、通常、固定資産税評価額により算定されます。そして、外壁塗装や水回りの工事、内装をきれいにする程度の部分的な改修工事の場合は、固定資産税評価額が改定されることはまずありません。これは、原則として、建物の床面積の増加あるいは減少を伴わないリフォーム工事や建物の基礎と柱を残しただけの改築工事が行われた場合には、建物の固定資産税評価額の改定が行われないためです。
だからといって、相続開始直前に、リフォーム工事を行った場合はどうかというと、国税庁のホームページに次のような質疑応答事例があります。
『増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価』
【照会要旨】
所有する家屋について増改築を行いましたが、家屋の固定資産税評価額が改訂されていないため、その固定資産税評価額が増改築に係る家屋の状況を反映していません。このような家屋は、どのように評価するのでしょうか。
【回答要旨】
増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない場合の家屋の価額は、増改築等に係る部分以外の部分に対応する固定資産税評価額に、当該増改築等に係る部分の価額として、当該増改築等に係る家屋と状況の類似した付近の家屋の固定資産税評価額を基として、その付近の家屋との構造、経過年数、用途等の差を考慮して評定した価額(ただし、状況の類似した付近の家屋がない場合には、その増改築等に係る部分の再建築価額から課税時期までの間における償却費相当額を控除した価額の100分の70に相当する金額)を加算した価額(課税時期から申告期限までの間に、その家屋の課税時期の状況に応じた固定資産税評価額が付された場合には、その固定資産税評価額)に基づき財産評価基本通達89(家屋の評価)又は93(貸家の評価)の定めにより評価します。(以下略)
つまりは、工事費用の70%で評価される可能性は残りますが、それでも、工事費用相当額を現金で持っている場合に比べると、相続財産の総額は減少することとなります。
では、生前にリフォームをすることなく、空き家控除を選択するのはどのような場合だろうかと考えますと、まずは相続税がかからない場合、そして、耐震基準をすでに満たしており、リフォームの必要がない場合となりそうです。(生前にリフォームを済ました場合も空き家控除の適用はあります。)
なお、空き家控除は、平成28年4月1日から31年12月31日の簡にした譲渡に適用するとありますが、かつ、相続開始があった日の属する年の12月31日の間にした譲渡とされていますので、平成25年1月2日以後に発生した相続から適用があるということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
明日1/17(日)は28年最初の相続カフェの日です
明日1/17日(日)は28年最初のオープンオフィス、相続カフェの日です。
相続カフェの日は、初回無料の税務相談を、予約なしで承っております。
また、相談なんて、かしこまって聞くほどのことではないけれども、ちょっと気になるあんなこと、こんなことを聞いてみようなんてこともできるのが、相続カフェの日のメリットです。
美味しいお茶とお菓子をご用意しております。ちょっと一服がてら、のぞいてみませんか?

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
原野…??
土地の現況調査をし、その土地の地目について迷うことがあります。
特に、登記上の地目が畑であるのに、実際は耕作をしなくなって年月が経ち、灌木などが生い茂っている様を見た場合、どのように評価しようかと思うことがありました。なぜなら、畑ではなく、それが原野であるならば、その土地の評価額がぐっと下がることとなるからです。
相続などで使用する財産評価基本通達では、その7で土地の評価上の区分について、「土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。」としていますが、「地目は、課税時期の現況によって判定する。」と指定することを忘れていません。そして注書きでは、「地目の判定は、不動産登記事務取扱手続準則第68条及び第69条に準じて行う。」としています。
では、その不動産登記事務取扱手続準則を見てみましょう。
68条では「第68条次の各号に掲げる地目は,当該各号に定める土地について定めるものとする。この場合には,土地の現況及び利用目的に重点を置き,部分的にわずかな差異の存するときでも,土地全体としての状況を観察して定めるものとする。」とし、それぞれの地目について説明しています。
そのなかで、畑とは「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」とあり、原野とは「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」とあります。ちょっと見ただけでは、疑問となった土地の区分としてよくわからない気がします。
しかし、「耕作の方法によらないで」とは、耕作に適さず、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたと解するようです。ですので、耕作をやめた畑に、雑草やかん木類が生い茂り、原野のような外観になったとしても、それは農地であり、原野ではないということのようです。
「耕作放棄地」は畑であって、「耕作不能地」が原野である。
実際は、もっと難しいところもあるようですが、簡単な目安として覚えておくとよさそうです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
賃貸用不動産を取得した場合の仲介手数料
会計検査院が、年末に恒例の税金の無駄遣いを指摘しています。
このうち、財務省に関するものは、税制改正に繋がったり、税務調査において注目事項となるため、チェックが欠かせません。
2014年度決算検査報告では、相続税額の2割加算(相続により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合に所定の方法により計算した金額にその100分の20に相当する金額を加算などした金額をその者の相続税額とするもの)洩れや有価証券の評価に関するもの、合計所得金額が2000万円を超えるのに、住宅取得資金の贈与特例を適用しているもの等が指摘されています。
ここで取り上げたいのは、不動産所得についてです。
個人が不動産を貸し付けた場合、受取家賃などの収入金額から必要経費等を控除した金額を不動産所得として、他の所得とともに申告します。しかし、個人が貸付けの用に供する不動産を取得する際に支払った仲介手数料は、賃貸のための経費ではなく、その不動産の取得価額に含めることになります。そして、不動産を譲渡するときに取得費として、譲渡収入から差し引くこととなるのです。
賃貸用不動産を購入した場合、このように不動産所得の必要経費でなく、その取得価額に含めなければならないものには、使用開始日までの期間に対応する借入金利息や固定資産税の精算金等があります。一方、不動産取得税や登録免許税、収入印紙などは不動産所得の必要経費となります。
取得価額に含めるべきものを必要経費に算入しないよう注意しましょう。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
空き家控除~相続により郷里の家を取得した場合
空き家問題がクローズアップされています。人口減少により、住宅が余るとされていましたが、その他にも高齢者が介護施設に入ったりすることにより、人が住まなくなった住宅が増えているようです。そして、このような空き家の発生原因として、相続の発生が挙げられています。
確かに相続により郷里の家を取得することとなった場合、相続人がその住居にすむことは多くなく、とはいえ、すぐに売却することも少ないことから、管理の行き届かない空き家を生じさせる結果となることとなります。
そういったこともあり、平成28年度税制改正大綱では、空き家に係る譲渡所得の特別控除として,相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が,一定の家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には,その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる特例を創設するとしています。
一見よさげな制度ですが、次のような要件が設けられています。
1.相続開始直前に被相続人の居住用家屋で被相続人以外に居住者がいなかった被相続人居住用家屋及びその敷地等を相続により取得したものであること
2.譲渡時に耐震リフォーム等をして現行の耐震基準をクリアしたものであること
中古住宅を譲渡する場合には、ある程度のリフォームをしなければ買い手がつかないとの現実もありますが、この特例の適用のためには、譲渡前のリフォームが前提となること、例えば、父に相続が発生した後、母が老人ホームに入居したため、空き家となった自宅を譲渡するような場合には適用がないことに注意する必要があります。また、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例、つまり、課税された相続税額の一部を控除できる制度とは、選択適用となるようです。
この制度は、国会の議論を経て、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用される予定となります。また、細かい内容については、今後の政令の公表を待つこととなります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産の一部のみ分割済の場合の相続税の申告
遺産分割協議が行われなかったりして、被相続人の遺産が未分割のまま、相続税の申告期限となった場合、いわゆる法定相続分などの民法の規定による相続分に従って財産を取得したものとして、相続税の課税価格を計算することとされています。
たとえば、親一人、子供3人の家庭で、親が亡くなったときに、子供たちの間で遺産分割が済んでいないならば、子供達がそれぞれ遺産の3分の1を取得したものとして、相続税の申告をすることとなります。
では、相続税の申告期限となったときに、遺産の一部しか分割されていない場合は、どのように相続税の課税価格を計算することとなるのかが疑問です。その場合も未分割の部分は民法の相続分に従って、各相続人が取得したものとして、計算するのでしょうか?
実は、遺産の一部が分割済の場合の課税価格の計算方法には、2つの方法があるのです。このように、すでに分割された部分を無視して、未分割部分だけで民法の規定による相続分で分けて計算する方法を積み上げ方式といいます。これに対して、すでに分割された財産と合わせて、民法の規定による相続分となるよう計算する方法を穴埋め方式といいます。
どちらの計算方法が正しいのでしょう。これについて、平成27年6月3日の裁決事例では、穴埋め方式が正しいとの判断がされました。課税実務では、このように穴埋め方式により計算せよとされていて、先例として最高裁平成5年5月28日判決があります。また、東京地裁昭和62年10月26日判決でも、穴埋め方式が支持されています。
穴埋め方式については、実務家を中心に、疑問とする意見も多々あるようです。しかし、現在のところ、穴埋め方式により相続税額は計算するということが、平成27年の裁決例で再確認されたということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
贈与税の配偶者控除
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。ただし、あくまでも、贈与税の特例ですので、登録免許税や不動産取得税は課されることとなります。
贈与税の配偶者控除の特例を使って、相続財産となりそうな居住用不動産を配偶者に移転することができます。また、その不動産に含み益があるならば、売却した場合の3,000万円控除の特例を、事前にその不動産の持分贈与をすることで、夫婦でダブル適用することも見込むことができます。なお、3,000万円控除とは、マイホームを売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例で、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ることが要件ですので、マイホームの敷地の持分と併せて、マイホーム自体の持分も、配偶者に贈与することがポイントです。
ところで、平成28年度与党税制改正大綱に次のものがあります。
贈与税の配偶者控除について、その適用を受けるための申告書に添付すべき 登記事項証明書を、居住用不動産を取得したことを証する書類に変更する。(注)上記の改正は、平成 28 年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る 贈与税について適用する。
つまり、贈与税の配偶者控除を受けるためには、従来、その贈与を受けた不動産の登記名義の移動が必須でした。ところが、今回の改正案では、不動産登記手続きは必要でなく、贈与契約書を作成し、税務申告書に添付することで、受けることができるとしています。
この改正により、相続発生直前や居住用不動産譲渡契約直前の贈与契約であっても、それが事実である限り、贈与税の配偶者控除の特例を受けることが可能となりそうです。いろいろな意味で、気にある改正事項ですので、どのような法案となるか注目したいところです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。