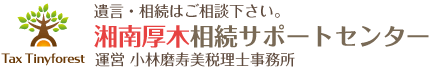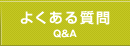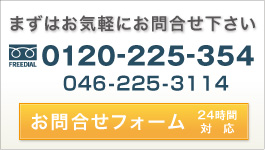Author Archive
生命保険料の贈与スキームと分割贈与
生命保険料の贈与スキームではでは、最初から保険料相当額を保険金受取人に贈与するという前提で行われるものです。そうすると、当初から保険料の総額を贈与するつもりで、毎年分割払いをしているとも考えることもできそうです。
その考え方が正しければ、保険料の総額相当額が保険料支払開始年に一括贈与されたことになります。となると、贈与税は超過累進課税ですので、負担する税額が当初の想定を大きく超えた金額となってしまいます。
しかし、このような分割贈与の認定は、現行税制では、贈与を行う期間が定められていること等により総額が算定される場合に可能となるものです。生命保険契約は保険事故発生により、以後の保険料の支払がないことから、贈与される保険料の合計額が確定せず、また、贈与期間も未定であることから、保険料の総額の贈与とはいえないとされています。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
生命保険料の贈与スキームとは?
生命保険料の贈与スキームでは、子や孫がその生命保険契約の契約者兼受取人となり、父母や祖父母が被保険者となります。子や孫が契約者ですので、保険料を負担するのも子や孫とです。つまり、子や孫の名義の預金口座から、保険料が引き落とされることになります。父母や祖父母が、その預金口座に毎年生命保険料相当額を送金する方法により、保険料相当額を贈与するのです。生命保険料の贈与の場合は、毎年の贈与額は生命保険料控除額程度とすることが多いようです。受け取った保険金については一時所得課税となり、保険金から支払った保険料の総額及び特別控除額50万円を控除した残額の2分の1に対して課税ということとなり、税メリットを受けることができます。
もし、毎年保険料相当額を送金することが面倒だということで、贈与する方の口座から引き落とされるようにしたならばどうでしょうか? このようにしてしまうと、保険料の負担者、保険金の受取人が、通常の生命保険金と場合と全く同様になりますので、受け取った保険金はみなし相続財産となります。
この生命保険料の贈与スキームにより保険金を受け取った場合に、相続財産でなく一時所得となることについての根拠となる裁決例があります。昭和59年2月27日の裁決例では、未成年者(13才)である子が、被保険者を父、保険契約者及び保険金受取人を自分として保険契約を締結したかたちとなっていますが、実際は父が親権者として、子に代わって契約手続きをしています。父は5年の間、子名義の普通預金口座に、現金を振り込む形で毎年の保険料相当額を贈与していました。年払いの保険料の金額は1,028,000円、毎年の入金額は100万円か110万円です。その後父に相続が発生し、保険金2,000万円及び配当金804,056円が子に振り込まれました。
所轄税務署長は、この保険金等を相続税の対象であるとしたのですが、審判所は子の一時所得であるとしました。この判断の決め手となったのは次の5点です。
(1) 保険事故発生により、保険会社から子に実際に保険金が支払われたこと
(2) 子が保険契約時には13才の未成年者であり、親権者である父と生計を一にして、その扶養を受けていたこと。
(3) 契約締結の交渉及び保険料の払込みの行為者は、親権者である父であること。
(4) 保険料は、父の所得税の確定申告に係る生命保険料控除において控除されていないこと。
(5) 子は、それぞれの年分において贈与税の申告書を提出し納税していること。
この裁決例がでたことにより、各保険会社は、生命保険料の贈与プランとして、この種の保険パッケージを提案しているようです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合
平成27年1月1日以降に、20歳以上の方が、父母や祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた場合、贈与税の税率が軽減されています。つまり、贈与税の税率は、平成27年1月1日以降は、2本立てとなっています。
この軽減された税率を特別税率といい、今までの税率を一般税率といいます。
特別税率の影響があるのは、410万円以上(基礎控除額110万円を控除後の金額が300万円以上)の贈与を受けた場合です。
注意点としては
1.「20歳以上」とは、その年の1月1日で20歳以上です。
2.その年に贈与を受けた金額の合計額が410万円を越えるときは、次のA、Bの区分に応じ次の書類の提出が必要になります。
A その贈与者からの贈与について、初めて特例税率の適用を受ける場合
贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類
つまり、その人の氏名、生年月日及びその人がその贈与者の直系卑属に該当することを証する書類です。
B その贈与者からの贈与について、前年以前において、既に特例税率の適用を受けるために上記Aの書類を贈与税の申告書又は更正の請求書に添付して提出している場合
提出した税務署名及びその年分を記載した書類
制度の適用を受けるためには、戸籍謄本等の提出が必要ですが、同じ贈与者からの贈与であれば、何度も同じ書類を提出する必要はないというのも、利用者にとってはいいところです。
一方、税務署側でも、相続開始前3年以内の贈与など、贈与の実態がより把握しやすくなるとの利点があることになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続発生以前死亡と以後死亡
お父様やお母様が亡くなられた場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者と子となります。お父様を亡くされた方をAさんとすると、法定相続人はAさんのお母様とAさんのご兄弟となります。
ここでもし、不幸にして、お父様が亡くなられる前にAさんの弟が亡くなられていたとします。この場合、弟さんの妻はお父様(義父となります。)と養子縁組していない限り、法定相続人になりません。しかし、弟さんに子がいるならば、その子は代襲相続人として、お父様の法定相続人となります。
ところが、弟が亡くなったのがお父様が亡くなられた後であり、そのときにお父様の相続について遺産分割協議が成立していなかったならばどうでしょう。その場合でもお父様の相続人はあくまでも弟さんです。しかし、弟さんの相続に関して、弟さんの妻と子は権利を引き継ぐため、弟さんの権利の承継人として、妻と子(通常は代表者)が遺産分割協議に参加することになるのです。そして、妻の権利はあくまでも弟さんの権利を引き継いだものですから、遺留分も有するということになります。
では次に、亡くなられた方に子がなく、両親もすでに先立たれていた場合は、亡くなられた方のご兄弟が法定相続人となります。もしご兄弟がこの場合の被相続人よりも先に亡くなられていた場合は、その方の子(つまり、甥・姪)が代襲相続人となります。そして甥・姪も被相続人よりも先に亡くなられていた場合、この場合は再代襲ということになりますが、甥・姪の子に再代襲はしないというのが民法の決まります。
しかし、甥・姪がこの場合の相続人より先に亡くなられていた場合、その子は甥・姪の権利を引き継ぎますので、遺産分割協議に参加することになるのです。
もっとも兄弟には遺留分がありませんので、代襲相続人にも当然に遺留分がありません。ですので。甥・姪の子が遺留分を主張することはできません。
少しややこしいですが、相続関係説明図をきちんと整備すると、このような関係も迷わず処理できることになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産の全容が判らないときの申告義務
相続人の間が疎遠になっていて、特に家を出た相続人と家を継いだ相続人がいる場合には、遺産分割についての争い已然の問題が生じることがあります。つまり、家を出た相続人は、遺産の全容すら教えてもらえないという事態です。そのような場合に、それぞれの相続人が別々に相続税の申告するとしても、家を出た方の相続人は何を申告すればいいか判らないので、どうやって申告するのだという疑問が生じます。
確かに相続財産が判明しなければ申告の仕様がないとも思えます。だったら、無申告でもいいのでしょうか?
こういった疑問に対し、大阪高裁平成5年11月19日判決では次のようにいっています。
「納税者に相続財産のい一部が判明し、それが基礎控除額を超えて申告すべき場合には、判明した分についてとりあえず申告をしたならば、その者に対し、全相続財産についての無申告加算税を課さないこととする一方、右の判明した分さえ申告しない者に対しては、残余の相続財産についての事情の如何を問わず、全相続財産を基にした「納付すべき税額」に所定の率を乗じた金額の制裁を課すこととしているのであって、これにより、無申告という事態を防止するための実効性をあげ、一部分だけでも期限内に誠実な納税申告書を提出するよう国民に促すとともに、その納税義務の適正かつ円滑な履行を確保し、健全な申告秩序の形成を図ろうとしているものである。」
つまり遺産の全容が判らない場合は、判る部分だけでも申告しなさいということなのです。さらに、仙台地裁昭和63年6月29日判決では、次のようにもいっています。
「納税者が相続の事実自体を知る以上、相続財産の内容を自ら調査して申告をし、具体的な租税義務を確定させることが要求され、結果としてこれができなかった場合には、正当な理由があると認められる場合を除き、行政上の制裁である無申告加算税を賦課されることもやむを得ないところである。」
要するに、できる限りの調査、努力をしたうえで、判った部分の申告をしなさいということです。家を継いだ相続人が遺産の全容を教えてくれない場合でも、無申告でいいとはされていない。そういう結論になります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税の申告書に同意しない相続人がいる場合
遺産分割協議が成立しない場合は、相続人のみなさんが合意して未分割で申告書を提出することすらできないこともあります。
しかし、相続税の申告書って、相続人全員が同じ申告書で提出するような様式になっています。となると、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の減額特例を受けたいと思っている相続人の方は困ってしまいます。それでなくとも、申告期限までに申告書を提出しなければ、無申告加算税というペナルティが課されてしまいます。
そのような場合はどうすればいいのでしょうか。その場合でもまずは、税理士に申告書の作成をご依頼下さい。そして、できあがった申告書を認めたくない相続人の方の押印欄はそのままにして、その他の相続人の方だけ押印して提出すればいいということになります。
押印のない申告書は無効ではないかと心配になられるかもしれませんが、相続税の申告書は、申告する義務のある人が、それぞれに署名押印できるようになっていますので、押印した者にとっては、要件を満たす申告書として取り扱われますが、押印をしていない者にとっては、申告書ではないということになります。
また、相続人の一部がAという税理士に依頼して申告書を作成してもらい、他の相続人がBという税理士に依頼して申告書を作成してもらって、それぞれに提出した場合も、どちらの申告書も署名押印した人にとって有効として取り扱われます。もっとも、そのような事態になった場合は、後始末も大変になりますが。
いずれにしても、分割協議がまとまらなくとも、申告書を提出しない理由とはならないということだけは、ご留意下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
今年6月以前に相続人となられた皆様へ
今年も早2か月を残すところとなりました。
相続税の申告書の提出期限は相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の亡くなられた日)から10か月以内となります。したがって、今年6月以前に相続が発生した場合、来年4月までには申告書を提出しなければなりません。
これから、3月にかけ、一般的な税理士事務所は繁忙期に入ります。年末調整や個人の方の確定申告業務が入ってくるからです。資産税中心の事務所も、譲渡所得の申告や不動産所得の申告が多くあります。
今年6月以前に相続が発生した場合、申告期限と税理士事務所の繁忙期が重なることになります。
申告相談、申告依頼を急がなければなりません。
現在、遺産分割協議がまだ成立していない場合は、分割の行われていない財産について、小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできません。しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
そういった意味でも、税理士へなるべく早く相談された方が安心です。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
海外不動産投資
この何年かの間に海外不動産投資を検討される方が増えてきたのかなと感じます。話題として耳にすることもありますし、今夏、大阪で女性税理士連盟の定期総会に出席した際、同じフロアで「減価償却を使ったタックスメリット」という名の証券会社のセミナーが行われているのを目にしました。
海外不動産投資には、次のような仕組みにより、節税メリットがあるとされています。
1.減価償却の活用によって節税効果を得られる
海外不動産であっても、日本での申告では、日本の減価償却制度が適用され、法定耐用年数により償却することになるのですが、中古不動産、特に法定耐用年数を過ぎた物件等を取得することにより、毎年の減価償却費を多くすることができます。これにより不動産所得が赤字になっても、給与所得などと損益通算ができ、その年の課税所得を減少させることができます。
2.売却時に低い税率が適用される
減価償却が早くできるということは、売却時に売却原価が少ないため、売却益が計上されるということになります。しかし、5年間以上保有してその後に売却するのであれば、譲渡所得の税率は20%の分離課税となります。
節税メリット以外にも、円安による為替メリットや資産の国際分散によるリスク回避などのメリットも考えられますが、デメリットとしても、コンサルタント会社や現地税理士への手数料の支払いが生じます。
また、海外に預貯金や有価証券、不動産など合計5千万円を超える財産を保有する人に「国外財産調書」の提出が義務付けられており、こちらの手続きもする必要があります。
(冒頭のホテル開催のセミナーは、この国外財産調書セミナーとセットになっていました。)
こうした中、「海外中古物件利用の節税策 富裕層に広がる」というNHKの報道がありました。会計検査院が平成25年の税務申告で海外に不動産を所有していた331人の高所得者を調べたところ、287人が減価償却費を計上しており、節税効果が高くなる償却までの期間が短い物件の購入を繰り返している人も確認されたということです。
ここ最近、会計検査院の指摘から税制改正が行われるというパターンができてきているように思います。海外不動産投資についても、何らかな節税封じ策がとられる可能性が高いと推測されます。年末の税制改正大綱を注目したいところです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
あつぎ国際大道芸2016と相続カフェの日
あつぎ国際大道芸2016と相続カフェの日
恒例のあつぎ国際大道芸が11月12日(土)と13日(日)に本厚木駅周辺にて開催されます。
にぎわい爆発!あつぎ国際大道芸2016開催!!(厚木市HP)
街中がお祭り気分で盛り上がる大変楽しい2日間です。
会場は、厚木公園、本厚木駅北口広場、一番街通り、厚木中央公園、サンパーク、中町公園、花の公園、アミューあつぎ、イオン厚木店前、本厚木駅南口。
当事務所の近くでも、パフォーマンスが繰り広げられます。
この13日(日)、当事務所では無料税務相談をはじめとした相続カフェの日を行います。イベントがてら、みなさんでおいでください。
例によって美味しいお茶とお菓子をご用意してお待ちしております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
タワーマンション節税
平成29年度税制改正で、政府・与党は20階建て以上の高層マンションについて、高層階の固定資産税と相続税を引き上げるとの報道がありました。
「タワマン節税」けん制、高層階は増税へ
18年以降の新築で 政府・与党方針
2016/10/25 0:36 日経電子版
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO08745040U6A021C1EE8000/
対象は大都市圏で増える「タワーマンション」と呼ばれる超高層物件で、20階建て以上を想定しているとのこと。
上記の記事では、資産評価システム研究センターが全国の新築高層マンションの分譲価格を調べたところ、最上階の床面積あたりの単価は最下層階より平均46%高かったとあります。
そもそも、タワーマンション節税法は、マンションの一部屋に対する土地の価格の占める割合が低いことを利用したものなのです。相続税の計算では、相続財産を財産評価基本通達で評価しますが、評価通達では、(1)建物については固定資産税評価額で評価すること、(2)共有物件については、持分割合で単純に按分することという計算方法になります。高層階か低層階で固定資産税評価額に差が設けられていないのです。
したがって、特にタワーマンションの高層階については、取得価額と相続税評価額に大きな差が生じるため、相続税の節税になるとされています。また、賃貸の用に供したら、建物は借家の評価となり、首都圏では30%減額となりますし、敷地は貸家建付地の評価になり、大体20~30%減額るという面もあります。
総務省が検討している新しい評価額の仕組みは、高層マンションの中間の階は現行制度と同じ評価額にする一方、中間階よりも高層の階では段階的に引き上げ、低層の階では段階的に引き下げるというものです。記事では、評価額5000万円の建物にかかる固定資産税は単純計算で年70万円。5500万円になれば固定資産税は年77万円に増えるとの計算例を示しています。
この節税防止策は固定資産税評価額を変えるもので、評価通達の改正はないようです。そもそも家屋の固定資産税評価は、再建築価格を基準とする方法が採用されており、階層による評価調整は評価額算定のどの段階で行うのか興味があります。
新しい税制の対象は18年以降に引き渡す新築物件に限定し、既存の物件は今の税制を適用することになります。では、タワーマンション節税のためには、今年から来年が買い時でしょうか?
確かに毎年課される固定資産税という意味ではそのようにいえるかもしれません。とはいえ、現行税制でも、タワーマンションを購入し、財産評価基本通達で評価した場合に、その評価額が適当でないとして、否認された裁決事例(平成23年7月1日非公開裁決例・東裁(諸)平23-1)や、最高裁の否認判決もあります(平成5年10月28日判決)。
相続開始直前にタワーマンションを購入し、相続開始後に売却するような場合には、課税上の弊害があるとして、現行税制でも否認されるということに留意する必要があります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。