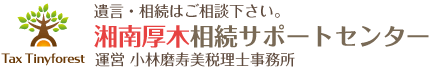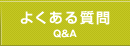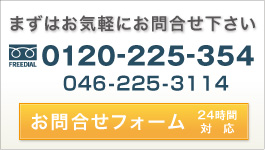Author Archive
割引電信電話債券
亡くなられた方の財産を整理しておりますと、日本電信電話公社の割引電信電話債券が出てくることがあります。
先日もそのような債券が出てきました。売出期間満了日 昭和54年9月29日、最終償還期限 昭和64年7月30日とあります。
民法上の債権の消滅時効は、10年と規定されています(民法167条第一項)。したがって、既に無価値となっているのではないかと疑われます。しかし、インターネット上に償還に成功したとする情報があり、その理屈が納得できるものでしたので、大丈夫と確信し挑戦していただくことにしました。
債券証書の裏面には償還窓口として、証券会社や銀行名が多数記載されていますが、現在ではすでになくなったものも多くあります。ですが、手当たり次第にこれらの銀行をあたっても、NTTに問い合わせてもうまくいきまん。結局は主幹事である日本興業銀行を引き継いだみずほ銀行で、償還していただくことができました。
手順としては、証書のコピーを銀行に預け、償還済みでないこと、事故債券でないことが確認された後、現物を提出して、取引口座に入金ということになります。地方の支店窓口で、手続きを完了させることができました。また、償還手続き自体の手数料はかかりません。
先に申しましたとおり、本来の消滅時効は過ぎていますが、時効を援用する手間との比較で、今でも償還可能となっているようです。
もし、そのような債券がでてきた場合は、あきらめずに挑戦してみてください。また、相続財産に加算することも忘れずに、ということになります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税
平成27年度税制改正大綱にて、結婚・子育て資金を一括贈与した場合に、贈与税を非課税とする特例の制定案が公表され話題となっています。
この案は、2年前に導入された教育資金贈与の特例が高反響だったことから、その適用範囲を広げたもののようにみえますが、そのアイデアは、先の教育資金贈与特例に関する法案成立時に遡ります。平成25年2月の自民、公明、民主の3党合意により、「子や孫に対してお金をまとめて渡す際に贈与税が一定額まで非課税とする措置の対象を、教育資金だけでなく、結婚や出産に関する費用も加えることを、来年度(平成26年度)の税制改正の検討課題とする」というものがありました。
いよいよ、こちらが導入されるといったところです。
結婚・子育て資金の特例では、20歳以上50歳未満の人に対し、直系尊属である父母や祖父母などが、結婚・子育て資金の支払に充てるために金銭等を拠出し、信託銀行などの金融機関に信託等をした場合に、1人につき1千万円(内、結婚資金は300万円)までは贈与税を非課税とするものです。拠出期間は平成27年4月1日~平成31年3月31日です。また、受贈者が50歳に達した場合などに、結婚・子育て資金管理契約は終了しますが、使い残した残額については、贈与税が課税されることとなります。
ところで、結婚・子育て資金とは、挙式費用、新居の住居費、引っ越し費用、不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、子の医療費及び子の保育料などとされています。これらは、扶養義務から「必要な都度」贈与された場合、基本的には非課税となります。
国税庁HPにも「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が掲載されています。
したがって、この制度の特例たる所以は、事前に一括して贈与できることにあります。
もしも、結婚・子育て資金管理契約が終了する前に、贈与者が死亡した場合、使い残した残額は、相続税の課税価格に加算されます。しかし、孫やひ孫に対するものであっても、相続税額の2割加算の対象とはされません。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ジュニアNISAと贈与
昨年末、平成27年度税制改正大綱が発表されました。
そのなかにジュニアNISAの創設というものがあります。
これは、20歳未満の人が開設するJ-NISA口座内で、少額上場株式等の配当や譲渡益を非課税とするものです。
年間の投資上限額は80万円、非課税投資総額は400万円(=80万円×5年間)です。
ところで、ジュニアNISAでは、そのイメージと異なり、開設者の年齢の下限がないようです。つまりは、生まれたばかりの赤ん坊でもOKなのでしょう。
そして、この投資上限額である80万円は、実際は両親や祖父母などが、贈与することになるのでしょう。
ここで気をつけなければいけないのは、ジュニアNISAについて、非課税となるのは、配当や譲渡益、つまりは所得税です。
投資額について、贈与税の対象外となるとは、大綱にも記載がありませんし、考えづらいところです。
となると、このジュニアNISAの開設者が、その年において他にも贈与を受けた場合、贈与税の非課税枠110万円を超える可能性があります。そもそも、投資額分の贈与を受けたことを失念することもあるかもしれません。
実際に法案が出たときに、手当てされる可能性が全くないわけではありませんが、今回の改正のちょっとした落とし穴です。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
27年1月の休日税務相談
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
さて、今月の休日相談日は次の日程となります。
17日(土)、18日(日)、24日(土)、25日(日)
事前ご予約のうえ(0120-225-354,046-225-3114)、お気軽においでください。
お待ちしております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
「平成25年分の相続税の申告の状況について」が公開されました
国税庁のHPで「平成25年分の相続税の申告の状況について」が公開されました。
これによりますと、平成25年中に亡くなられた方は約127万人、相続税の課税対象となった方は約5万4千人(平成 24 年約5万3千人)で、課税割合は 4.3%(平成 24 年 4.2%)となったそうです。
そして、被相続人1人当たりの課税価格は2億 1,362 万円(平成 24 年2億 510 万円)です。
ただ、この資料には、一番人数の多い課税価格についての情報がありません。
そして、被相続人1人当たりの税額は、 2,824 万円(平成 24 年 2,380 万円)となっています。
興味深いのは、 相続財産の金額の構成比です。相続財産の金額の構成比は、土地 41.5%(平成 24 年 45.8%)、現金・預貯金等 26.0%(平成 24 年 25.6%)、有価証券 16.5%(平成 24 年 12.2%)の順となっています。
しかし、相続財産の金額の構成比の推移をみますと、明らかに土地の割合が減少し、現金・預貯金の割合が増加してきています。
例えば、平成6年の現金・預貯金の割合は9.4%、土地の割合が70.9%です。25年のデータと比較すると、差がはっきりします。
実務実感としましても、金融資産の割合の高い案件が増えてきているように思います。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
地主さんの相続~被相続人の収入?相続人の収入?
地主さんが亡くなられた場合、不動産所得の収入を、どのような基準で、被相続人のものと相続人のものとに分けて、申告すればいいのですかと質問されることがあります。
賃貸契約書で当月分の地代をその末日に支払うこととなっており、末日に相続が開始した場合ならば、迷うことはありません。でも、その月中、たとえば、20日に相続が発生したならば、どのように考えればいいのですかということです。
地代などの不動産賃料は、物の使用の対価として受けるべき金銭ですので、法律的にいうと、法定果実に該当します。法定果実について民法では、これを自分のものとして受け取る権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得するとされています。
ですから、20日に相続が発生した場合、1日から20日までの賃料は、被相続人に権利があり、21日から末日までの賃料は、相続人に権利があるということになります。
となると、所得税の申告も同じでしょうか?
所得税では、その年分の総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされています。「その年において収入すべき金額」といわれても、わかりにくいですね。
通達では、不動産所得の総収入金額の収入すべき時期について、「契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日」としています。つまり、当月分の地代をその末日に支払うこととなっているのでしたら、20日に相続が発生した場合は、前月分の地代までが被相続人の収入として、今月分の地代は相続人の収入として申告することとなります。
もう一つ気になるのは、相続税の取扱いです。所得税の取扱いでは、1日から20日まで地代も、相続人の収入として申告するということですが、民法では、1日から20日までの地代は、被相続人が受け取るべきものとしています。
だったら、所得税の取扱いにかかわらず、1日から20日までの地代は、被相続人の財産、つまり相続財産にならないのでしょうか。
これについて、相続財産を評価するときのきまりとなる財産評価基本通達では、相続財産として評価するとしていません。このことから、1日から20日までの地代は、相続税が課税される財産とはされていないということになり、所得税の申告と矛盾しないようになっているのです。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税の調査の状況と預金口座の発見
平成25年度に実地調査が行われた相続税についての申告状況が公表されました。平成25年度の調査ですので、平成23年及び24年中に発生した相続事案が中心となります。
実際に実地調査がされたのは11,909件です。申告漏れ等があった件数が9,809件、全体の82.4%が何らかの申告漏れ、評価間違いなどがあったことになります。
申告漏れ相続財産の金額の内訳は現金・預金等が最も多く、その次は土地との報告ですが、実際の相続財産自体も現金・預金等が多く、また、土地と異なり、取引の少ない金融機関の口座などは遺族にとっては発見しにくいとの事情があるかと思います。
では、被相続人の預金の調査はどのように行えばいいのでしょうか。
基本的にはまず預金通帳から調査を開始します。預金通帳が残っていた場合、たとえそれが古いものであっても、取りあえずはその銀行の支店に、口座の有無の確認をし、口座が存在していた場合には残高証明書の発行を依頼します。その際、依頼者が相続人であることの確認がされますので、自分と被相続人との関係が明らかになる戸籍謄本や住民票などを持っていく必要があります。
また、過去勤務していた会社の近所の銀行の支店なども口座が残っている可能性が高いです。最近では預金通帳なしの口座などもありますので、パソコンの履歴、クレジットカードや通信販売の振り替え口座なども確認する必要があります。また、取引がないと思っても、一応郵便局の口座の有無も確認しておくといいでしょう。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税の申告要否の簡易判定シート
早いものでもう11月も半ば、相続税の基礎控除の改正まで、2か月を切りました。
国税庁のHPに平成27年分用の「相続税の申告要否の簡易判定シート」と「相続税のあらまし」がアップされています。
この「相続税の申告要否の簡易判定シート」は、亡くなられた方のご家族の数や相続財産の総額などを記入し簡単な計算をすることにより、相続税の申告が必要かどうかの判定ができるようになっています。
とはいえ、相続財産の金額をどのように出していいのか、これだけでは分かりませんので、併せて「相続税のあらまし」を参照する必要があります。
この「相続税のあらまし」がなかなか優れものです。たった4ページながら、相続税の計算の仕組み、相続人となるのは誰か?、相続税のかかる財産は何か?、生命保険金を受け取った場合は?、生前に贈与された財産がある場合は?、相続財産から控除できる債務は?、
といったことから、簡単な財産評価の方法、自宅の土地などについての評価の減額特例(小規模宅地等の減額特例)まで、網羅しています。
文字が詰まっており、一般の方にはなんだか取っつきにくい印象ですが、一度目を通してみられてはいかがでしょう。
国税庁HP「相続税の仕組みの分かりやすい解説「相続税のあらまし」」

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
医療費控除と債務控除
所得税の確定申告の際、医療費控除だけ受けられる方も多いかと思います。
医療費控除として、自身の所得金額から控除できるのは、自分の分、妻又は夫の分、そして、生計を一にする親族の分を支払った場合です。
この「生計を一」というのは、簡単に言えばお財布が共通ということです。ですので、親族の分を「支払った」というのは、この共通な財布から出て行ったということを意味し、病院の窓口で、実際に自分の財布から、直接支払った場合に限りません。
相続が発生した場合、亡くなられた被相続人について、その亡くなられた年の医療費を誰の所得から控除するかという問題があります。
当事務所にて、ご依頼を受ける相続の場合も、通院中であったり、何度か入退院をされていた方がほとんどです。生前は、ご本人や配偶者が医療費をお支払いになり、病院で亡くなられ、最後の医療費を親族の方が精算されています。
この医療費は、誰の所得から控除することができるか、ということです。
例えば、26年6月3日に相続が発生したとします。26年中は、2月10日に8万5千円、4月26日に5万3千円、そして、亡くなられた後、6月5日に3万6千円の医療費を支払ったとします。これらの医療費は、すべて、亡くなられた方の預金から支払いました。となると、すべて、亡くなられた方の、26年の所得税の確定申告(=最後の確定申告、準確定申告)で、所得金額から控除することになるのでしょうか。
答えは否です。
医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ、亡くなられた方の預金などから支払われた場合であっても、亡くなられた方が支払ったことにはなりません。
したがって、2月に支払った分、4月に支払った分については、亡くなられた方の、準確定申告で、所得金額から控除することができるのですが、亡くなられた後、6月5日に支払った3万6千円については、準確定申告で控除することはできません。
では、亡くなられた後で支払った医療費はどうなるのか。その医療費を負担した親族が、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人が受けた時に、被相続人と生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人であるその親族の医療費控除の対象となります。
設例の場合ですと、医療費を支払った被相続人の預金を取得した人が、通常は医療費を負担した人となります。
さらに、この医療費は、被相続人の債務ですので、その医療費を負担した親族が相続人や包括受遺者(相続時精算課税の適用を受ける贈与により財産をもらった人を含みます。)で、日本国内に住所がある方ならば、相続税を計算するときは、遺産総額から差し引くことができます。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
11月21日「後発的事由の税務」セミナーをします。
「後発的事由の税務」セミナーでは、何らかの事情変更があった場合に税がどのように対応するかについてお話しします。
例えば、遺産分割協議完了後に財産を発見した場合、簡単に考えれば、その発見した財産を新たに誰が取得するかを決めればいいということになります。
しかし、そんな財産があるのだったら、当初のような分割協議案にしなかったといった場合もあることでしょう。その場合に、始めから遺産分割協議をやり直したらどうなるか。もちろん、民法的にはOKです。でも、税は……。
他に、被相続人が締結した契約を無効とする調停があった場合、被相続人に係る保証債務が発覚した場合などなどをお話しします。
日 程 2014/11/21(金) 13:30~16:30 (受付開始13:00)
会 場 ビズアップ総研 セミナールーム
(東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター10F)
料 金 会員以外・・・16,200円
お問い合わせ (株)ビズアップ総研(担当:小西)TEL: 03-3569-0968
事前お申し込み制です。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。