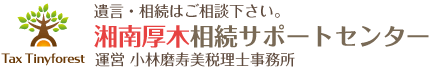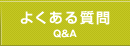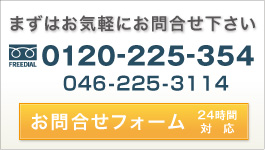Author Archive
相続財産を売却して分ける場合
遺産が実家の自宅と敷地というような場合に、相続人の間で、現金化して分けようと決まったとします。では、実際の売買の手続きはどのようになるのでしょうか。
おそらく、相続人のうちの一人が代表者として、仲介業者や売買の相手側と交渉することとなると思います。そして、話がまとまって、実際の売買契約となる場合も、売主として、相続人の全員がサインするよりも、この代表者一人がサインをすることとなるでしょう。
そうなると、売買契約書を見た場合に、遺産を相続人の一人が相続して、代償金を他の相続人に渡している、つまり代償分割なのか、遺産を相続人の全員が相続して、売却代金を全員で取得した、つまり換価分割なのか、分からない場合があります。
換価分割か代償分割かでは次のようにその後の課税関係が全く異なりますので、遺産分割協議書にどちらであるか明記するなどして、相続人の間で明らかにしておくことも重要です。
| 代償分割 | 換価分割 | |
| 遺産の帰属 | 代償分割義務者のみ | 共同相続人 |
| 遺産を譲渡した場合の譲渡所得税 | 代償分割義務者のみ | 共同相続人全員 |

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割の方法
実際に相続が発生した場合において、まず遺族の間で行われるのが遺産分割協議です。いわゆる形見分けのように、被相続人の財産を1つ1つ、各相続人に配分する方法を現物分割といい、もっとも基本的でシンプルな遺産分割の方法となります。
しかし、実際は相続財産の大部分を1つの不動産が占める場合や、被相続人の事業を相続人の一人が承継する場合などでは、現物分割は困難ですので、代償分割や換価分割の方法を採ることとなります。
代償分割とは、遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が、取得しなかった他の共同相続人などに対して債務を負担する方法です。債務を負担するといいましても、通常は自分自身の預金などから代償金として、幾ばくかの金銭を支払うことが一般的です。遺産分割においては、この代償分割の方法が採られることが、実際は多いのです。
換価分割とは、共同相続人全員が未分割の財産を譲渡、つまり売却し、譲渡代金を相続人で分配する方法です。換価分割では、共同相続人全員に相続税の他に譲渡所得が発生することとなり、その処理には注意が必要となります。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続セミナー(暦年贈与と贈与特例)27.8.16開催
平成27年8月16日の相続カフェでは、14時~「暦年贈与と贈与特例」のセミナーを開催します。
気取らない、わかりやすいお話ですので、どうぞお気軽にご参加下さい。
お越し頂いた皆様には、平成27年度税制改正の要点解説の本を差し上げます。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続カフェを開催します
月遅れの送り盆、8月16日(日)に小林磨寿美税理士事務所にて、相続カフェを開催します。
美味しい東北のお菓子を食べながら、相続、贈与についてお話しをしましょう。
・平成27 年の路線価を確認してみましょう。
・相続税の計算の仕組みを確認しましょう。
・暦年贈与と5つの贈与特例についてお話しします。
・その他何でも相続・贈与についてのご相談に応じます。
・どなた様でもどうぞお気軽においでください。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
27年6月の税務相談
ことしも約半分を過ぎようとしています。
6月の休日税務相談は、7日(日)、13日(土)、14日(日)、20日(土)、27日(土)、28日(日)を予定しております。
どうぞ、お電話等にてご予約の上、お越し下さい。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続税申告要否判定コーナー
国税庁のホームページに、相続税の申告要否判定コーナーが開設されました。
これは、ホームページ上で画面の案内に従い、法定相続人の数や相続財産、被相続人の債務や葬式費用、3年以内贈与財産の価額を入力することにより、課税される遺産総額を計算し、相続税の申告が必要かどうかを判定するものです。
したがって、現時点では、申告をすることによって適用できる特例である小規模宅地等減額特例や配偶者の税額軽減特例の計算まではしていません。もっとも、7月以降に両特例の適用記載例の公表も予定しているようです。
入力のために必要な書類も掲げていますので、あらかじめそれらの書類を用意して、入力スタートをすると、スムースに判定ができます。
あくまでもこのようなコーナーは、相続税の申告要否を大まかに判定するものですが、具体的な数値を把握することができますので、利用されてみてはいかがでしょう。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
3月の休日相談会
3月の休日相談会は、4日、14日、28日・29日を予定しております。どうぞ、ご予約のうえ、おいでくださいますようお願いします。
また、平日も随時ご相談に応じておりますので、ご遠慮なくお電話下さいませ。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
2月の休日相談会
2月の休日相談会は、7日・8日、15日、21日・22日を予定しております。どうぞ、ご予約のうえ、おいでくださいますようお願いします。
また、平日も随時ご相談に応じておりますので、ご遠慮なくお電話下さいませ。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
生命保険等の一時金の支払調書と契約者変更記載
生命保険契約では、保険料負担者である「保険契約者」、保険事故発生の対象とされる「被保険者」、そして、「保険金受取人」の三者が誰であるかにより課税関係が変わります。これについては、本サイトを参考にして頂くとして、ここでは、保険期間中に保険契約者を変更した場合の課税関係について述べてみようと思います。
生命保険契約等について契約者の変更があった場合には、次のような課税関係が発生します。
(1) 死亡による契約者の変更
契約者と被保険者が異なる生命保険契約等について、契約者が保険期間中に死亡した場合、新しく契約者となった人がその契約の権利を引き継ぐことになります。このため、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額(解約返戻金相当額)が相続税の課税対象となります。
(2) 死亡によらない契約者の変更
旧契約者の死亡によらない契約者の変更であれば、その時点では課税関係は生じません。契約者に対して、被保険者の死亡や満期等により保険金等が支払われたときに、初めて相続税や贈与税、所得税等の課税対象になります。
○ 受取保険金のうち保険金受取人以外の者が負担した保険料相当部分
受取保険金のうち、保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額の保険事故発生の時までに払い込まれた保険料全額に対する割合に相当する部分は、その保険料負担者から、相続又は贈与により取得したものとみなされます。
○ 受取保険金のうち保険金受取人が負担した保険料相当部分
保険金受取人の所得税(一時所得)及び住民税の対象とされます。一時所得の計算では、受取保険金のうち保険金受取人が負担した保険料相当部分から、受取人が負担した部分の金額を控除し、さらに50万円を差し引いた金額の二分の一が課税対象となります。
ところで、現在、生命保険会社等から税務署に対して支払調書が提出されるのは、次の場合です。
(1) 1回の支払金額が100万円を超える死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等が支払われた場合
(2) 同一人に対して1年間に20万円を超える年金給付金が支払われた場合
つまりは保険契約者を変更したとしても、生命保険会社等から支払調書は提出されません。
そのため、次のような問題が生じていました。
(1) 死亡による契約者変更の場合
生命保険契約に関する権利について、相続税の課税漏れとなることがありました。
(2) 死亡によらない契約者変更の場合
全額を一時所得の収入金額とし、旧契約者が負担した払込保険料を含む保険料の全額を収入を得るために支出した金額として、控除し申告している場合があります。
極端なケースでは、保険事故発生直前に契約者を変更することにより、本来、受取保険金相当額を新契約者が旧契約者から贈与されたとみなされるにもかかわらず、一時所得の申告で済ませている場合もあります。
そこで、平成27年度税制改正大綱では、生命保険契約等の一時金の支払調書等について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載するという項目が入れられています。
(1) 保険会社等は、生命保険契約等について死亡による契約者変更があった場合には、死亡による契約者変更情報及び解約返戻金相当額等を記載した調書を、税務署長に提出しなければならないこととされます。
(2) 生命保険金等の支払調書について、保険契約の契約者変更があった場合には、保険金等の支払時の契約者の払込保険料等を記載することとされます。
この改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用される予定です。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
新刊「相続税申告で迷いがちな債権・債務」
「相続税申告で迷いがちな債権・債務~法務・税務の取扱いと留意点」という本を書きました。
清文社より2015年1月13日発刊、小林磨寿美著、ISBN:978-4-433-52234-6 定 価:2,592円(本体2,400円)です。
どのような相続であっても、被相続人に債権・債務がないものはありません。
しかし、それについて、正面から取り上げた実務参考書がとても少ないと感じていました。
本書は、「相続税の申告における債権・債務について、基本的考え方、債権・債務に関する帰属の判断の仕方から、財産評価のノウハウ、準確定申告の注意点まで、裁決例・裁判例を多く取り上げポイントを解説。」したものです。
よろしければ、ご購入頂き、お読みいただければと願っております。

神奈川県厚木市に開設以来、厚木・海老名・座間・大和・綾瀬・相模原・愛川・秦野・平塚・寒川・町田・横浜を中心に、相続税申告から遺産分割協議、不動産の名義変更、民事信託まで、ワンストップでお手伝いしております。
当事務所は、初回相談を無料とし、ご家族の思いや将来の安心を大切にするヒアリングから、ご希望に合わせたプランをご提案。
税務調査や生前対策にも対応し、専門家との連携で正確な土地評価や信頼のプランニングをご提供します。
落ち着いたサロンで、気軽に相談できる雰囲気を心がけています。大切な思いをしっかり受けとめて、地元と共に歩んでいます。
まずはお気軽にお問い合わせください。