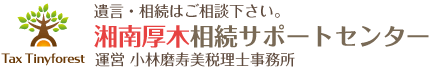Archive for the ‘相続税・贈与税関係’ Category
エステートプランニング
相続対策のために生前贈与や生命保険の加入、遺言などをする場合があります。しかし、実際に行われているものを見ますと、対策として行われているものが、個別に関連なく行われており、全体として見た場合の視点が欠けているように思います。
必要なのは総合的な生前相続対策です。エステートプランニングと言われることもあります。このエステートプランニング、アメリカなどの例ですと、撤回不能信託(トラスト)とジョイント・テナンシーを利用したものが多いようです。トラストを利用すると、検認裁判不要で相続人に財産を移すことができること、財産を承継させたい人に確実に財産を遺せることなどから、エステートプランニングでは、トラスト利用が必須とされているようです。
さらに、州法によっては、撤回不能信託とした場合、遺産から外すことができるため、有効な相続対策になるのです。しかし、残念ながら日本では、撤回可能信託か撤回不能信託かによる税制上の区別はなく、委託者と受益者が異なることとなったときに課税関係が発生するということになります。
そうであっても、信託が有効な生前対策の1つであることは、これまでもご説明したとおりです。
もう一つのジョイント・テナンシーというものですが、こちらは、不動産等を所有する場合によく使われる形態で、各所有者はそれぞれ所有権を等分に持つというものです。ただし、共有とは異なる合有財産権(Joint Tenancy)という権利に基づくものです。
合有財産権は、(1)同一の不動産に関する同一の譲渡行為によって(unity of title)、(2)2名以上の者が同一の時に始期を有する(unity of time)(3)同一の権利(unity ofinterest)を(4)共同所有する(unity of possession)という、4つのunity(同一性の要件)を備えた財産権と説明されています。しかし、この最大の特徴は、合有権者の1人が死亡した場合、その有した権利が相続の対象とならずに生存する他の合有権者に帰属することにあります。
もっともこれが、日本でも有効であるかというと、ジョイント・テナンシーという権利は日本にはありませんが、かの国でそのような権利を形成していた場合、我が国でも民法的な権利関係としては、被相続人の相続財産を構成しないということはいえます。
しかし、税法的には、被相続人の合有不動産権が移転したことによる生存合有不動産権者の権利の増加は、「対価を支払わないで利益を受けた場合」に該当するため、生存合有不動産権者が移転を受けた被相続人の合有不動産権の価額に相当する金額については、被相続人から贈与により取得したものとみなされることになるとされています。つまりみなし贈与、あるいは遺贈ですね。
それならば、ジョイントテナンシーは相続対策としてダメかというと、争族対策としての利用がないわけではない。大事なのは、各手法にどのようなメリットとデメリットがあり、どのように組み合わせると、全体として有効な対策となるかということをプランニングすること、それがエステートプランニングということになります。
公正証書遺言の執行と遺言書預りサービス
公正証書で遺言をしても、心配なのはその遺言通りに処理が行われるかというところでしょう。そのような場合に対応し、遺言執行者を指定する方法があります。遺言者自身で遺言執行者を指定するには、その遺言書で指定する必要があります。
遺言執行者は、相続開始後に相続に関する手続きを単独で行う権限があります。たとえ、他の相続人が遺言執行者を無視して、相続財産を勝手に処分したとしても、それらの行為は無効となります。また、その相続人に対し、何かしらの措置を取ることもできます。
また、遺言執行者の指定がない、一般の相続による名義変更の手続きは何かと面倒です。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議書の作成だけでなく、それぞれの機関に要求される書類の収集や記載、署名押印手続きが煩雑です。遺言執行者を指定していれば、執行者が相続人代表として手続を進められるので、この煩雑な手続きから解放されます。
公正証書遺言には原本、正本、謄本があります。原本は公証人が保管し、正本と謄本が遺言者側に渡されます。謄本は原本のコピーと考えて下さい。正本はこれにより実際の手続きができるものです。当事務所では公正証書遺言作成の支援サービスを行っており、執行者に指定された場合は、この正本の保管も10年間1万円で行っております。
家族信託の弱み
家族信託は任意後見の異なり自由度のきいた財産の管理を実現すること、実現性の高い遺言の役割を担うこと、相続などにより共有状態となった財産の出口戦略に役に立つことなどの利点があり、そのため最近特に注目を集めています。
とはいえ、家族信託には、家族信託の弱みがあります。
まず、信託ですから、委託者、受益者だけでなく、受託者が必要です。受託者はもともとの財産の所有者(委託者)に代わって信託財産を管理するのですから、それなりの事務の手間がかかります。もしかしたら、適当ななり手がいないかもしれません。
また、受託者に財産の所有権が移ること、受託者が財産を管理することについて、他の利害関係者から異議がでるかもしれません。例えば委託者兼受益者が父、受託者が長男の場合に次男が面白くなく思うかもしれない。しかしそのような場合は、次男が信託監督人、つまり、受益者のために受託者の監督を行う者になることにより、問題は解決することになります。しかし、次男に時間がない場合は、他の人に信託監督人をお頼むわけですが、こちらのなり手がないということもありえます。
2つ目は、家族信託に向いているのは、信託という契約の性質上、財産の管理に関することだということ。つまり、生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うのでしたら、任意後見と組み合わせた方がよさそうです。
3つ目は、権利関係が複雑な物件については、家族信託では荷が重いということ。信託では受託者に財産の所有権が移りますので、抵当権がついた物件では、金融機関などの同意が必要です。関係者が多くなるほど同意を得なければならない者が増え、契約条項も増えてきます。
家族信託についても、先の相続を見越した生前対策の一つの手法ですので、それぞれの強み弱みを、それぞれのケースにあてはめ、場合によっては、複数の手法を組み合わせることにより、威力を発揮することになります。
収益物件の持分相続における家族信託の利用
被相続人に貸しアパートや駐車場などがある場合に、遺産分割で個々の物件毎に相続人が取得するとなると、不平等が生じたりするため、共有にて取得するとの方法が採られることがあります。
しかし、共有状態にある不動産の管理運用に当たっては、将来的にその不動産の管理や処分で足並みが揃わなくなったりすることがあります。ことがこじれて、共有物の買取りをする業者などが介入してきたりするとさらに問題が複雑になってしまします。
そこで、信託のしくみの利用により、管理権や処分権の制限をしたり、移転をすることにより、これらのコントロールを容易にすることができます。また、跡継ぎ遺贈型信託の利用により、これらの収益物件を、妻から子へと円滑に引き継がせることも可能です。
例えば、父、母、子3人といった家族構成で考えてみます。父が貸しアパート等の収益物件を保有しているとします。生前に、父(委託者)はこれらの収益物件を信託財産とし、子の一人を受託者とし、自分を受益者として信託契約を結びます。その際、将来何らかの要因により、受益者である父が意思表示のできない状態となったときに備えて、受益者の指示なく管理運用可能のように定めることもできます。
さらに、この契約で、父(受益者)死亡に備えて第二次受益者、第三次受益者を定めることができます。この第二次受益者に受益者の妻(母)、第三次受益者に子3人というように定めていくこともできます。つまり、遺言のような機能を持たせることになりますので、このような信託を、遺言代用信託といいます。しかし、遺言が自分の死後のことしか決められないのに対し、信託では、上記のようにその後の財産の行方まで指定することができるのです。
なお、仮に次男を受託者とすると考えた場合、第二次相続の際、受託者が受益者を兼ねることになり、それはどうかなという疑問が生じるかと思います。しかし、この例のように、受益者が複数人の場合は、受託者の一人が受益者と兼ねることも可能です。
この信託契約において、当初は委託者(父)=受益者(父)の自益信託でしたが、父の相続発生により、母が受益者の地位を引き継ぐことになります。母は対価なしにその受益権を相続により取得していますから、ここで相続税の課税が発生することになります。母の相続発生により受益権を取得することとなる子たちについても、同様に相続税の課税が発生します。このあたりは、現物資産を相続した場合も、信託受益権を相続した場合も同じと考えて下さい。
この信託契約では、最終的に子3人が共有者のような関係になりますが、共有物件のときと異なり、管理権、処分権は契約によりコントロールされます。ところで、子についても、相続が開始する時が来るわけですが、どのタイミングで信託を終了させるのかは、契約により決めることができるので、共有物件のように持分が細分化されることも防ぐことができます。
家族信託の仕組み~相続後、相続前の財産の管理
相続発生後に残された配偶者など、ある程度の財産をお持ちの高齢者の財産の管理について、有効といわれる家族信託はどのような仕組みになっているのでしょう?
ここでいう家族信託というのは、信託銀行を介さない家族による信託というものです。
信託は、3つの要素でなっています。それが、委託者、受託者、受益者です。
委託者は財産を持っている方です。この財産は、1,000万円程度の銀行預金とか自宅とかでも構いません。
受託者は、この財産の管理運用を任された方です。受益者とは、この財産から利益を得る者です。
私たちは、ものを所有することで、直接利用することによる利益、貸したりした場合は運用による利益、処分することによる利益などを得ます。信託では、ものを所有する権利と、ものを所有することにより利益を得る権利とを分解して考えていきます。
あくまでもイメージとしてですが、名義は○○さんですが、でも実質自分のものだよといった感じです。
受託者は託された財産を管理するわけですが、この名義を取得することになります。そして。受益者がそのものの利益を実質的に取得するわけです。
家族信託の基本形は、財産を所有する親(委託者)が、財産を管理する子(委託者)に財産を信じて託し、その財産から生じる利益を受ける(受益者)こととなります。つまり、委託者=受益者となるもので、このような信託を自益信託といいます。
自分が直接所有している場合とどこが異なるか、それは管理する子が入り込むことです。所有権(名義)事態は子(委託者)に移動することになります。子に所有権が移動することで、勝手に処分されないか不安も残るかもしれませんが、そこは、管理できる範囲を信託契約で決めればいいのです。
また、受託者がちゃんと仕事をやっているか管理する信託監督人を設けることもできます。
気になる税金ですが、実質的に使用収益する権利は受益者=委託者に残ったままですから、基本的にこの段階では、所得税などの税金の課税関係は変わりません。
ではスムースに受託者が財産を管理するにはどうすればいいか、不動産などは信託登記できますが、預金の場合は預金通帳の屋号に「信託口」と入れ てくれる銀行を選んで口座開設することで解決します。
家族信託による財産管理はこのような仕組みで行うことになります。
成年後見か家族信託か
相続が発生し、いろいろな相続手続きを済ませた後で問題となるのは残されたご高齢の相続人の今後です。
とくに、後に残されたお母様やお父様の財産の管理については、今は大丈夫だけれども、将来的には成年後見などを考えなければいけないのかなあと、不安を抱えていらっしゃるご家族の方も多いかと思います。
確かに、近頃では財産の処分については、金融機関、保険会社、不動産仲介業者等々、手続きが厳しくなりました。基本的に本人が書類に自書(署名だけで済まないことも多いのです)することができなければ、手続きを進めることが難しくなっています。
そして、そのような場合には、後見人をつけることなどが求められるのですが、後見人が付くと本当に財産を使うことに厳しくチェックされることになります。ちょっとした出金もなかなか難しくなると覚悟する必要がでてきます。
そこで、最近注目を集めているのが家族信託です。家族信託とは、資産を持つ方が、自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理などの目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。この不動産は、自宅だけしかない場合でも大丈夫なのです。
家族や親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。処分できる財産の自由度も増します。
イメージとして、たまにみんなに食事をごちそうしたときに、ファミレスでというのが任意後見制度、カニなんかもというのが家族信託でしょうか。
相続後の財産の管理や二次相続対策で、家族信託が最近注目を集めているのはこのような理由です。
生命保険料の贈与スキームと分割贈与
生命保険料の贈与スキームではでは、最初から保険料相当額を保険金受取人に贈与するという前提で行われるものです。そうすると、当初から保険料の総額を贈与するつもりで、毎年分割払いをしているとも考えることもできそうです。
その考え方が正しければ、保険料の総額相当額が保険料支払開始年に一括贈与されたことになります。となると、贈与税は超過累進課税ですので、負担する税額が当初の想定を大きく超えた金額となってしまいます。
しかし、このような分割贈与の認定は、現行税制では、贈与を行う期間が定められていること等により総額が算定される場合に可能となるものです。生命保険契約は保険事故発生により、以後の保険料の支払がないことから、贈与される保険料の合計額が確定せず、また、贈与期間も未定であることから、保険料の総額の贈与とはいえないとされています。
生命保険料の贈与スキームとは?
生命保険料の贈与スキームでは、子や孫がその生命保険契約の契約者兼受取人となり、父母や祖父母が被保険者となります。子や孫が契約者ですので、保険料を負担するのも子や孫とです。つまり、子や孫の名義の預金口座から、保険料が引き落とされることになります。父母や祖父母が、その預金口座に毎年生命保険料相当額を送金する方法により、保険料相当額を贈与するのです。生命保険料の贈与の場合は、毎年の贈与額は生命保険料控除額程度とすることが多いようです。受け取った保険金については一時所得課税となり、保険金から支払った保険料の総額及び特別控除額50万円を控除した残額の2分の1に対して課税ということとなり、税メリットを受けることができます。
もし、毎年保険料相当額を送金することが面倒だということで、贈与する方の口座から引き落とされるようにしたならばどうでしょうか? このようにしてしまうと、保険料の負担者、保険金の受取人が、通常の生命保険金と場合と全く同様になりますので、受け取った保険金はみなし相続財産となります。
この生命保険料の贈与スキームにより保険金を受け取った場合に、相続財産でなく一時所得となることについての根拠となる裁決例があります。昭和59年2月27日の裁決例では、未成年者(13才)である子が、被保険者を父、保険契約者及び保険金受取人を自分として保険契約を締結したかたちとなっていますが、実際は父が親権者として、子に代わって契約手続きをしています。父は5年の間、子名義の普通預金口座に、現金を振り込む形で毎年の保険料相当額を贈与していました。年払いの保険料の金額は1,028,000円、毎年の入金額は100万円か110万円です。その後父に相続が発生し、保険金2,000万円及び配当金804,056円が子に振り込まれました。
所轄税務署長は、この保険金等を相続税の対象であるとしたのですが、審判所は子の一時所得であるとしました。この判断の決め手となったのは次の5点です。
(1) 保険事故発生により、保険会社から子に実際に保険金が支払われたこと
(2) 子が保険契約時には13才の未成年者であり、親権者である父と生計を一にして、その扶養を受けていたこと。
(3) 契約締結の交渉及び保険料の払込みの行為者は、親権者である父であること。
(4) 保険料は、父の所得税の確定申告に係る生命保険料控除において控除されていないこと。
(5) 子は、それぞれの年分において贈与税の申告書を提出し納税していること。
この裁決例がでたことにより、各保険会社は、生命保険料の贈与プランとして、この種の保険パッケージを提案しているようです。
平成27年以降に父母などから財産の贈与を受けた場合
平成27年1月1日以降に、20歳以上の方が、父母や祖父母などの直系尊属から財産の贈与を受けた場合、贈与税の税率が軽減されています。つまり、贈与税の税率は、平成27年1月1日以降は、2本立てとなっています。
この軽減された税率を特別税率といい、今までの税率を一般税率といいます。
特別税率の影響があるのは、410万円以上(基礎控除額110万円を控除後の金額が300万円以上)の贈与を受けた場合です。
注意点としては
1.「20歳以上」とは、その年の1月1日で20歳以上です。
2.その年に贈与を受けた金額の合計額が410万円を越えるときは、次のA、Bの区分に応じ次の書類の提出が必要になります。
A その贈与者からの贈与について、初めて特例税率の適用を受ける場合
贈与により財産を取得した人の戸籍の謄本又は抄本その他の書類
つまり、その人の氏名、生年月日及びその人がその贈与者の直系卑属に該当することを証する書類です。
B その贈与者からの贈与について、前年以前において、既に特例税率の適用を受けるために上記Aの書類を贈与税の申告書又は更正の請求書に添付して提出している場合
提出した税務署名及びその年分を記載した書類
制度の適用を受けるためには、戸籍謄本等の提出が必要ですが、同じ贈与者からの贈与であれば、何度も同じ書類を提出する必要はないというのも、利用者にとってはいいところです。
一方、税務署側でも、相続開始前3年以内の贈与など、贈与の実態がより把握しやすくなるとの利点があることになります。
相続発生以前死亡と以後死亡
お父様やお母様が亡くなられた場合、法定相続人は亡くなられた方の配偶者と子となります。お父様を亡くされた方をAさんとすると、法定相続人はAさんのお母様とAさんのご兄弟となります。
ここでもし、不幸にして、お父様が亡くなられる前にAさんの弟が亡くなられていたとします。この場合、弟さんの妻はお父様(義父となります。)と養子縁組していない限り、法定相続人になりません。しかし、弟さんに子がいるならば、その子は代襲相続人として、お父様の法定相続人となります。
ところが、弟が亡くなったのがお父様が亡くなられた後であり、そのときにお父様の相続について遺産分割協議が成立していなかったならばどうでしょう。その場合でもお父様の相続人はあくまでも弟さんです。しかし、弟さんの相続に関して、弟さんの妻と子は権利を引き継ぐため、弟さんの権利の承継人として、妻と子(通常は代表者)が遺産分割協議に参加することになるのです。そして、妻の権利はあくまでも弟さんの権利を引き継いだものですから、遺留分も有するということになります。
では次に、亡くなられた方に子がなく、両親もすでに先立たれていた場合は、亡くなられた方のご兄弟が法定相続人となります。もしご兄弟がこの場合の被相続人よりも先に亡くなられていた場合は、その方の子(つまり、甥・姪)が代襲相続人となります。そして甥・姪も被相続人よりも先に亡くなられていた場合、この場合は再代襲ということになりますが、甥・姪の子に再代襲はしないというのが民法の決まります。
しかし、甥・姪がこの場合の相続人より先に亡くなられていた場合、その子は甥・姪の権利を引き継ぎますので、遺産分割協議に参加することになるのです。
もっとも兄弟には遺留分がありませんので、代襲相続人にも当然に遺留分がありません。ですので。甥・姪の子が遺留分を主張することはできません。
少しややこしいですが、相続関係説明図をきちんと整備すると、このような関係も迷わず処理できることになります。